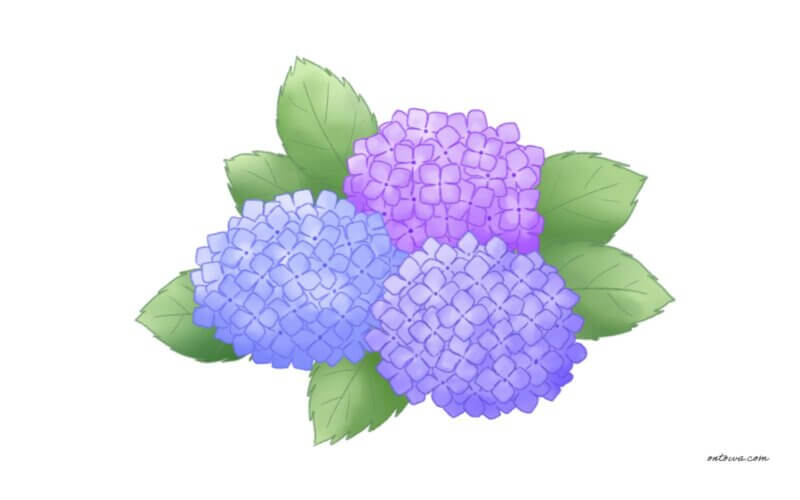日本の暦に合わせて作られた暦日である雑節のひとつ、入梅(にゅうばい)。
気象上では「梅雨入り」といい、私たちにとって馴染みにある言葉になります。
その名の通り、季節が梅雨に入る頃を知らせる暦日で、太陽暦では毎年6月11日ごろにあたります。
旧暦では、二十四節気の第九、芒種から数えて初めの壬(みずのえ)の日と定められていました。
梅雨は「ばいう」とも読み、語源は「黴(かび/ばい)をもたらす雨」を意味する「黴雨」であったと言われていますが、梅が熟す頃の雨を意味する「梅雨」の方が、より日々に喜びをもたらしてくれるような語感ですね。
じめじめとした天気が続く頃はなんとなく気分も沈みがちですが、昔から伝わる知識や、季節に応じた過ごし方から、雨の季節を心地よく過ごすヒントを探してみましょう。