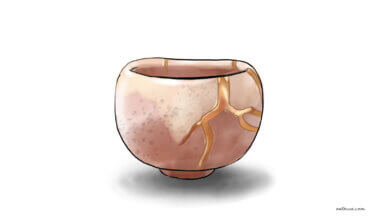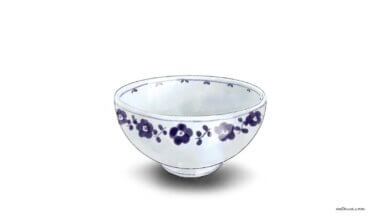太古の縄文時代から現代に至るまで、日本各地で脈々と受け継がれてきた陶芸。
その中でも、平安時代後期ごろにはじまり、今現在も制作活動が続いている代表的な六つの窯元を「六古窯(ろっこよう)」と呼びます。
その六つの窯元とは、瀬戸焼、常滑焼、信楽焼、越前焼、丹波焼、備前焼です。
すべての産地においてその土地や周辺地域で採掘した原料を用いており、それぞれの技法も、陶工たちに受け継がれてきました。
2017年には日本遺産にも認定され、六古窯を知ることは日本の文化における教養の一つともみなされています。
今回は、この六古窯を一つずつ学ぶ前の導入編です。
コンテンツの内容