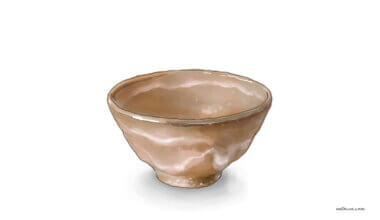九州地方では、16世紀末から磁器作りが始まり、有田焼をはじめとした高品質な白磁が生み出されてきました。
長崎の三川内焼も、この400年前から続く陶芸の歴史に連なる、日本を代表する白磁の産地のひとつです。
三川内焼(みかわちやき)、別名平戸焼と呼ばれるそのやきものは、純白の透けるような肌と、繊細で流麗な染付や、透かし彫り、彫刻的な造形を用いた立体的な装飾が特徴です。
「超絶技巧」という言葉がぴったりな三川内焼は、慶長3年(1598年)に平戸藩主の松浦鎮信(まつらしげのぶ)が豊臣秀吉によって引き起こされた「慶長の役」の際に連れ帰った多くの朝鮮陶工たちが平戸藩の保護の下で陶磁器製造に励んだことからはじまりました。
この陶工たちにより、日本のやきものは躍進を遂げ、現代にも続く伝統陶芸が数多く生まれました。
今回は、この山形鋳物の魅力や伝統を紐解き、心地よい暮らしのヒントをさがしてみました。