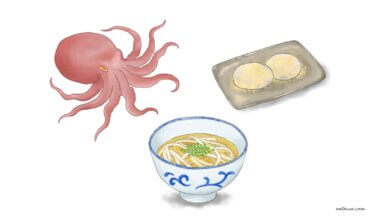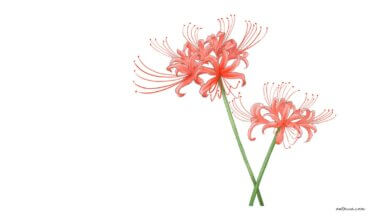すべてのいのちの源である、水。
人間の体は約60%が水分と言われており、私たちは日々、水の恩恵を受けて生きています。
洗うための水、飲むための水、料理するための水。私たちの暮らしに欠かせない水は、昔からさまざまなかたちで使われ、信仰されてきました。
日本神話には、水や海を司るスサノオノミコトや龍神、天水分神(あめのみくまりのかみ)といった水の神が登場します。
これらの神々は、水に関連する豊穣や災害を祈願・鎮めるために祀られており、水が日本人の暮らしにおいて重要な位置を占めていることがわかります。
古代日本において水の神は、川や海があばれて襲いかかってくる恐ろしいイメージと、作物を育てて生命をはぐくむという尊いイメージの両方があります。
自然は今でも人の力の及ぶところではありませんが、現代のように水道や治水が整う前は、どのようにして水と付き合ってきたのでしょうか。
今回は、水にまつわる和の心を感じるエピソードから、心地よい暮らしを探してみました。