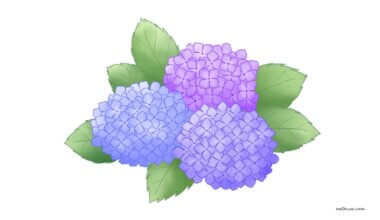主に農業の時期の目安として伝わってきた日本の雑節のひとつ、「二百十日(にひゃくとおか)」は、立春から数えて二百十日経つ頃にあたります。およそ九月一日ごろであり、古来から日本列島に台風が来襲する頃として知られています。
稲が開花する頃と台風の風水害が起こる季節が重なり、海もしけて漁に悪影響が出るため、農家や漁師にとって二百十日は厄日です。そのために、日本各地の神社では風鎮祭(風祭り)が行われることも。
近年では気候変動の影響で海面水温が上がり、台風が強い勢力を保ったまま日本列島に上陸することが増えているといいます。
二百二十日は、「三大厄日」の一つとして知られています。
三大厄日とは、「二百十日」、「二百二十日」、そして「八朔(はっさく)」のことを指し、これらの日は災厄が起こりやすいとされ、新たな事を始めるのを控える風習があります。
今回は、この二百十日、二百二十日について学び、家の中でもできる限り心やすらかに居られるよう、台風の日に心地よく過ごす方法についても考えてみましょう。