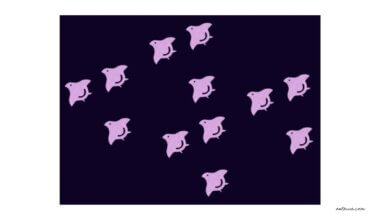「象嵌(ぞうがん)」とは、地に模様を彫り、そのくぼみに別の素材をはめ込む加飾技法の総称です。
「象」は「かたちづくる」、「嵌」は「はめ込む」を意味し、木工や陶磁、金工などあらゆる素材の工芸品に用いられ、金工の場合は金や銀などの貴金属の色彩や、打痕の隆起によって模様を表現します。
金工の象嵌技法は、中国大陸から朝鮮半島を経て、飛鳥時代に日本列島へ伝わったという説があります。しかし、古墳時代の刀剣類などの遺物に象嵌が施されていることが確認されていることもあり、起源はより古い可能性もあるようです1。
日本の刀剣といえば、侍を象徴する刀です。
刀は現代では美術品として扱われているように、精密な意匠が凝らされています。
そして刀の装飾のなかでも、鞘に収めて腰に挿している時に最もよく見える鍔(つば)には、武器とは思えないような優美な象嵌が施されていることがあります。
特に、全国的に美術工芸が発展した17世紀以降の江戸時代では、「鍔は肥後」と呼ばれるほど肥後象がんの刀鍔が人気を誇りました。
今回は、現代の熊本県の伝統的工芸品である肥後象がんについて紐解きつつ、武士の美学について探りを入れてみましょう。