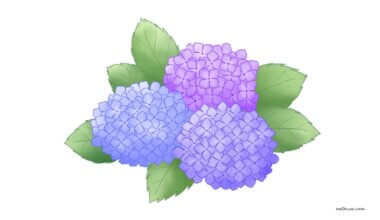奈良時代に伝わり宮中行事として始まった、季節の行事である五節句。一年に5回あるなかで、最後の節句となるのが9月9日の重陽の節句(ちょうようのせっく)です。
桃の節句で桃の花の鑑賞をする、また端午の節句で菖蒲湯の薬効を得るように、五節句では季節の植物が登場します。重陽の節句もまたの名を「菊の節句」といわれ、菊の花が持つという長寿の薬効にあやかる菊酒や菊枕、そして菊の花を鑑賞する菊合わせなど、菊の花の魅力を最大限に楽しむのです。
また、他の節句では子供が主役であることが多いですが、重陽の節句はいわば大人が主役となる節句。
今回は、ゆったりとした心地よい重陽の節句の過ごし方について、歴史や由来などをまじえながらお話しします。