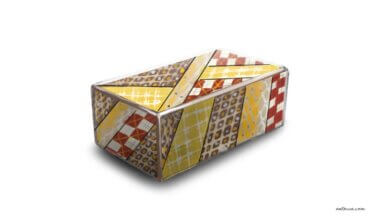人類史の中でも、太鼓は最も古い楽器といわれています。ナイジェリアのヨルバ地方では言語として太鼓の音が使われていたり、シベリアではシャーマンの太鼓は魂の乗り物であるとされ、病気の治療のために用いられていたなど、世界中の文化の中で重要な役割を担ってきました。
日本においても、太鼓の歴史は非常に古く、縄文や弥生時代の遺構から太鼓に用いたと思わしき土器や、太鼓を叩く姿の埴輪が見つかっていることから、古代にはすでに太鼓を用いた儀礼が行われていたと考えられています。
現代でも、全国各地の盆踊りや夏祭り、寺や神社の儀礼から、民俗芸能の田楽まで、日本の古今東西のあらゆる場面において、太鼓の響きが伝えられてきました。
今回は、太鼓の歴史を紐解きながら、心地よい日本の暮らしに伝わってきたリズムを探ってみました。