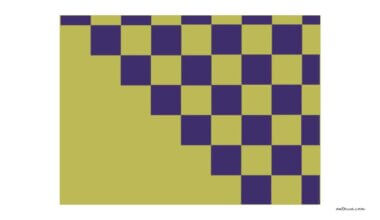日本では、鋳造技術が伝わった弥生時代前期末(紀元前400年-紀元前300年)から、農具や武器、仏具などの鋳物が作られはじめました。
この技術は今も受け継がれており、特に歴史が古い鋳物が山形県の山形鋳物といわれています。
平安時代中期(1058年から1065年)に源頼義が奥州を転戦した時、彼に従っていた鋳物師たちが京都への帰途から離れて山形に留まり、そこで鋳物製作を始めたとされる伝説があります1。
伝説では、頼義に従軍していた当時の鋳物師たちは軽さが重要な武具を手がけていたためか、軽量で薄く繊細なデザインの鋳物を得意とし、その特徴が現代にも伝わっています。
分業制を取らず、一つの工房が全ての工程を手がけることから、鋳物師の家によって作品の個性が異なることも山形鋳物の魅力。
今回は、この山形鋳物の魅力や伝統を紐解き、心地よい暮らしのヒントをさがしてみました。