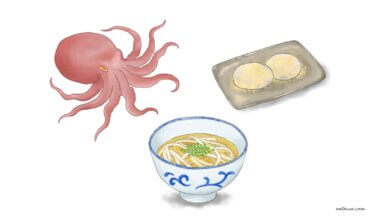「ふせぎ」と聞いて、それが何かわかるでしょうか。おそらく、若い世代にはなかなか見当もつかないものだと思われます。
ふせぎとは、古来日本の村境に吊るされていた藁(わら)のオブジェのことです。「防ぎ」からきた言葉であり、村に災いが来ないように祈る呪(まじな)いの一種で、主に関東地方のおもに東京の北西から埼玉県にかけて見られる風習です。
一説には、18世紀の江戸時代に疫病が蔓延した際、村を守るために始まったといわれており、現在でも指定文化財として残っているものも。
今回は、ミステリアスなこの風習について、調べてみましたので、ご紹介します。